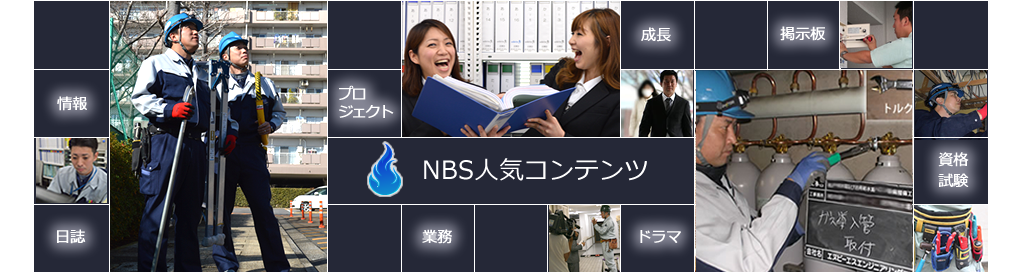NBSの連載小説 第三弾 僕シリーズについて

Episode 13 手が届かなかったもの
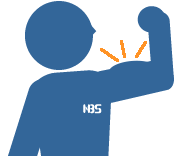
 「先輩、このソファーどこに置きます?」
「先輩、このソファーどこに置きます?」
「あ、テレビの正面において」
「先輩、この箱は?」
「それはこっちの子ども部屋に頼む」
「先輩、いい間取りですね~」
さっきから「先輩」と呼ばれているのは僕。
呼んでいるのは、後輩たちだ。
僕が、かつて働いていた業界の先輩の誘いを断り、消防設備士として生きて行く決意を嫁に伝えたあの夜から6年が過ぎようとしていた。
この間に僕は、特類も含めた消防設備士の資格をすべて取得、第一種電気工事士にも受かって、目下、電気工事一級施工管理技士を目指し勉強を続けている。
当時よちよち歩きだった息子は今年小学2年生、3つ違いで産まれた娘は保育園児、仕事に復帰した嫁と二人三脚で子育て真っ最中。公私ともにあわただしくも、充実した毎日を送っている。
そして今日は、新居へ引っ越しするため、会社の後輩たちが手伝いに来てくれていた。
とはいえ、近所からの引っ越しだし、物を余分に持たない主義の嫁のおかげで、アパートから持ってくる荷物も多くはなく午後には運び込みが終わり、段ボールを脇によけて引っ越しそば……焼酎が始まった。そば焼酎は先輩からの粋な差し入れだった。
多くの物を持ちたがらないからといって、物欲が弱いわけではない嫁は、「良いものを長く使う」というポリシーで、引っ越しを機に家電や台所用品を一新。慎重に吟味して選んだこだわりの調理家電や鋳物の鍋などを駆使して、ごくシンプルだけど飛び切りうまいツマミを並べてくれた。
新しい皿が出るたびに「先輩は、幸せですね~」とからかう後輩たちの声を心地よく聞きながら、「その通りだ」と思う。
「うわ~、この窓からの眺め最高!」子どもと遊んでくれていた後輩が、娘を両手で高々と頭上にあげたまま、顎で窓の外を指した。
立ち上がって外を見ると、下町らしい密集した街灯りと遠くに見える高速道路が、それなりの夜景を描き出していた。すぐ足元には、新婚当初に暮らしていたアパートの屋根も見える。
 僕がローンを組んで買った家は、転職を考えていたあの寒い夜に暗い気持ちで見上げた分譲マンションの最上階だった。
僕がローンを組んで買った家は、転職を考えていたあの寒い夜に暗い気持ちで見上げた分譲マンションの最上階だった。
あの時は、到底手が届かないと思っていた暮らしは、意外と近くにあった。
楽して来れたわけではない。プロフェッショナルとして結果を求められる厳しさは業界時代以上だった。しかし、自分の将来を信じて確実に歩みを進められる安心が、努力を継続する力になった。
人は、どこに行きつくのかわからないまま歩くことはできないのだ。かつて僕が少し上の先輩たちを見て、自分の3年先、5年先を想い描いてきたように、今の僕が後輩たちの道標となることができればと思っている。
■このコンテンツは、特定のスタッフを描いたものではなく、全員の経験をもとに書き起こしたフィクションです。NBSの社風に関しては、かなり忠実に描いています。