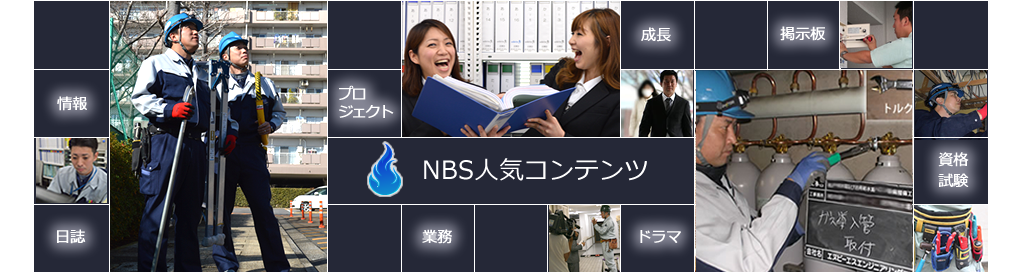NBSの連載小説 第三弾 僕シリーズについて

Episode 10 天国と地獄
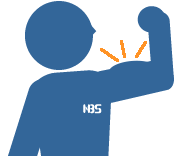
出火場所は、ゴミ置き場だった。
一週間の間に貯められた資源ゴミに何者かが火を点けたそうだ。
第一発見者は、新聞の配達員。朝刊を配ろうと、そのマンションに向かっていた彼は、1つ前の信号で煙に気づきすぐさま119番通報。エントランスから、消火器を取ってきて初期消火を試みるもなかなか消えず、1階の消火器を更に3本かき集めて、消し止めたとのこと。
 僕が運転する隣で、先輩が電話で話しているのはNBSの事務責任者。受話音量の設定のせいなのか、話す声が大きいからなのか、言葉がほぼ聞きとれる。ましてや今回は、「火災が発生しました」からはじまったとあって、車内はシーンと会話に聞き入っていた。
僕が運転する隣で、先輩が電話で話しているのはNBSの事務責任者。受話音量の設定のせいなのか、話す声が大きいからなのか、言葉がほぼ聞きとれる。ましてや今回は、「火災が発生しました」からはじまったとあって、車内はシーンと会話に聞き入っていた。
「現場検証も清掃もすんだが、この後どうすればいいか」と管理人から連絡があったと事務長が続ける。
「こっちは対応できます。材料も揃っています」と先輩。
放火の疑いが強いとなると、今夜消火器がないわけにはいかないとの判断で、僕らは点検順を繰り延べて、現場に急行することになった。
このマンションは、先々週点検したばかりで、消火器を点検したのは、当然ながら僕。今回使用された消火器も、もちろんそれに含まれている。「そうか、僕が点検した消火器が、初期消火の役にたったのか。そうかそうなのか」と、僕は何度も心の中で繰り返していた。消防設備点検は、消防法に定められた基準に沿って、設備などが設置されているか、それが正しく機能するかを確かめるためのものと思っていた僕は、頭を強く殴られたような気がしていた。
「実際に火災が起きたときのことを想像して点検するんだ」そう社長から繰り返し言われていたことが、ものすごい勢いで腹落ちした瞬間だった。
実際そのマンションでは、一階の消火器が観葉植物で隠れていたため、どちらの通路からも角を曲がらなくても見えるように、鉢の位置をずらした物件だった。何気なくやった一作業が、秒単位で時間を争う現場では、重要な役割を果たしたかもしれない。
僕がこの仕事を選んだこと。正しく点検ができたこと。実際に消火に役立ったこと。そのことをぐるぐるとらせん状に数えながら、徐々に天にも登るような高揚感に満たされ、僕は現場に降り立った。きっと特撮ヒーローの俳優みたいなキメ顔だったに違いない。
「使われた消火器はどこですかっ!」管理人に聞く声がいつもより心なしか低い。
笑いをごまかして咳払いをしている先輩を横目に見ながら、僕は使われた消火器4本を颯爽と駐車場に並べた。
「さぁ、僕。これからどうする?」と先輩。
「え…えっと詰め替えます」と僕。
「そうだな。じゃ、やって」
「!?!?!?」
消火器の薬剤を詰め替えるのは、これがはじめて。僕のドヤ顔は、一気に自信なさげな新人顔にもどってしまった。
このマンションに設置されている消火器は加圧式。
まずは、消火器の外形と内部を確認し、サイホン管、ホース、キャップと部品を隅々まで点検し、問題がないので薬剤を詰めていくことに。先輩の手順を見た後、あとの3本は任せてもらえることになった。
「粉が細かいから注意しろよ」
「わかってます!」
 1本目は、静かにふわっと薬剤が本体に入っていった。2本目は、まるで吸い込まれるかのような華麗な充填。気を良くした僕は、速さも技術の一部であることを思い出し、少々急いで薬剤を注ごうとした。勢いが早すぎた薬剤はジョウロからこぼれ、モクモクモクとピンクの粉煙を立ち上らせた。
1本目は、静かにふわっと薬剤が本体に入っていった。2本目は、まるで吸い込まれるかのような華麗な充填。気を良くした僕は、速さも技術の一部であることを思い出し、少々急いで薬剤を注ごうとした。勢いが早すぎた薬剤はジョウロからこぼれ、モクモクモクとピンクの粉煙を立ち上らせた。
その光景に驚きながら、「ああ、この煙はどこかでみたことがある。そうだ、黒沢映画の『天国と地獄』。身代金を入れたカバンを燃やすとピンク色の煙が出る仕掛けで、焼却炉から煙が出たのを三船敏郎がみつけるんだ」。「モノクロフィルムに着色して、煙だけピンクにしたんだぞ、すげーよな」と熱く語っていた前職の先輩の顔が急に蘇る。元気かな…先輩…。
「おい、おいっ!」
はっと我に返ると、先輩が半分に目を細めてこっちを睨んでいた。目を見開いているときも怖いが、半分になったときのほうがもっと怖い。
「すすすいません!」急いてはことを仕損じる。盛大に撒き散らした薬剤を、現場用の掃除機で掃除しながら、この作業で伸びてしまうこの後の予定のことを考えて、僕は深く深く反省したのだった。
■このコンテンツは、特定のスタッフを描いたものではなく、全員の経験をもとに書き起こしたフィクションです。NBSの社風に関しては、かなり忠実に描いています。