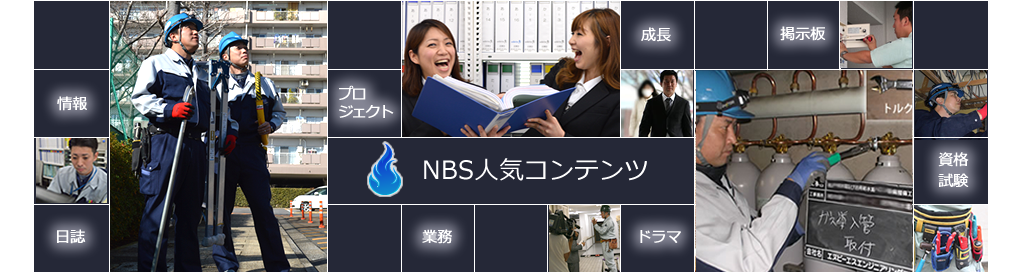NBSの連載小説 第三弾 僕シリーズについて

Episode 2 「大丈夫」と言う時は大丈夫じゃない時
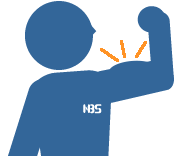
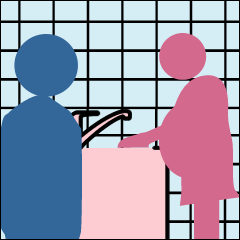 「仕方ないよ」
「仕方ないよ」
次の日の朝、謝る僕に嫁は静かに微笑んだ。いっそのこと怒ってくれればいいのに。伏し目がちな横顔がやけに悲しげに見える。
「ごめん」。もう一度言う。他に言葉が見つからない。
「私は大丈夫。それより君の疲れた顔のほうが心配」
そう言って洗い物をはじめた嫁の背中に、「だ…大丈夫だよ」と返したものの、語尾が力なく水音にかき消されてしまう。家族で住むには狭すぎるアパートの台所は、嫁の身長には少し低すぎ、彼女の顔をいつもうつむかせる。いつにも増して下向きに見える嫁の顔を、僕は覗き込むことができなかった。
人が「大丈夫」と言う時は、大抵の場合大丈夫じゃない時だ。特に、聞かれて返した「大丈夫」ではなく、自分から「大丈夫」と言っている場合は注意が必要だ。自分の中から沸き起こる「大丈夫なのか?」に答えている証拠であり、それだけ不安を抱えていることになる。これまで辞めて行った後輩たちに僕はそれを学んだ。そういえば、最近自分も「大丈夫っすよ」を連発しているような気がする。
「このままじゃいけない」。
 それから数日後、珍しく10時前に仕事が終わり、先輩と僕は屋台のおでん屋で肩を並べていた。
それから数日後、珍しく10時前に仕事が終わり、先輩と僕は屋台のおでん屋で肩を並べていた。
おでんつゆの中に浸して温めるアルミ容器の熱燗を茶碗ですすりながら、空腹を通り越した胃袋におでんを放り込んでいた。熱々の種で舌を火傷しそうだが、口にものを入れていないと、何か言ってはいけない言葉が出てきそうな沈黙があった。
7割がた胃袋が満たされてきたあたりで、先輩が唐突に言った。
「お前、会社辞めようと考えているなら、早いほうがいいぞ」
「へ?」「だだだ大丈夫っすよ」頬張ったばかりの竹輪を片頬に移動させてモゴモゴと返す。いつもは、漫才のコンビのようにボケ・ツッコミを応酬し合う関係だが、突然過ぎてうまい返しが見つからない。
「大丈夫?最近口癖になってないか?来年子ども生まれるんだろ。まともな仕事見つけろ。それに、お前が転職を考えはじめてていることは、もうとっくにわかってるよ」
先輩は、僕の茶碗になみなみと酒を注いで「おじさん、熱燗もう一本」と静かに言った。おじさんは、飲みさしの一升瓶を持ち上げた手をおろして、屋台の下から新しい一升瓶を出して栓を抜いた。
「門出に乾杯だ。おじさんも飲んで」
陽気に振る舞う先輩に、僕は何も言えなかった。僕が転職を躊躇して来た理由は、僕が辞めた後、先輩に大きな負荷がかかるのが目に見えていたからなんだ。
■このコンテンツは、特定のスタッフを描いたものではなく、全員の経験をもとに書き起こしたフィクションです。NBSの社風に関しては、かなり忠実に描いています。